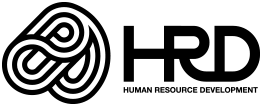パフォーマンスの起点は「人」——職場の成功を導く“人的要因”を解き明かす
原文:Performance Starts with People: Unlocking the Human Drivers of Workplace Success
変化が常態化した今日、組織はレジリエンス(回復力)、イノベーション、生産性の維持に努めています。しかしWiley Workplace Intelligenceの最新データによれば、長期的な成功の鍵は、システムや戦略だけにあるのではなく、「人」にこそあるのです。
人と人がどれだけうまく協働できるか。それはあらゆるビジネスの根幹であり、組織の持続性を支える要となります。かつて「ソフトスキル」と呼ばれていた能力——建設的なフィードバック、対立のマネジメント、他者のエンパワーメント、変化への適応、チームの動機づけ——はいまや、健全な職場文化をつくる基盤として、重要性が再認識されています。
この5か月間にわたる調査を通じて、私たちは一貫した真実にたどり着きました。それは、従業員が「心理的に安全である」「信頼されている」「明確な方向性が示されている」と感じているときにこそ、パフォーマンスが発揮されるということです。
不確実性の続く時代において、職場における“人のダイナミクス”への投資が、いかに組織の文化を強くし、持続的な成功をもたらすのか。そのヒントを、本記事でご紹介します。
組織文化における「建設的なフィードバック」の力
建設的なフィードバックを「伝えること」と「受け取ること」は、健全なチームダイナミクスの核となるスキルです。Wiley Workplace Intelligenceが実施した調査によると、フィードバックの頻度は、マネジメントの有効性や信頼関係の醸成、そして従業員の成長に深く関係しています。多くの従業員が率直なフィードバックを求めている一方で、その真価は「どれだけ頻繁に届けられているか」にあります。週1回以上のフィードバックがある場合、92%の従業員が「サポートされている」と感じるという結果が出ました。
マネジャーが定期的に関わることで、スキルのギャップを早期に見つけ、的確なトレーニングを提供しやすくなります。そうした継続的な関わりは心理的安全性を高め、フィードバックを「批判」ではなく「成長の手段」として機能させます。また、信頼と一体感も深まり、フィードバックを受け入れやすく、行動にもつながりやすくなります。
フィードバックの“すれ違い”が生む溝

毎週フィードバックを受けている人の92%がマネジャーに支えられていると感じているのに対し、
年に1度しかフィードバックを受けていない人では、そう感じているのは59%にとどまる
「週1回以上フィードバックを受けている社員の92%が、マネジャーに支えられていると感じている」のに対し、「年に1度しかフィードバックを受けていない社員では、そう感じているのは59%にとどまる」という調査結果があります。
この差を埋める鍵となるのが、マネジャーへのトレーニングです。実際、70%のマネジャーは何らかのフィードバック研修を受けたことがあると答えていますが、正式なプログラムを受講したのは41%に過ぎません。そして、正式なトレーニングを受けたマネジャーは、そうでない人よりも「自信がある」と答える割合が14ポイント高くなっています。
自信のあるマネジャーは、チームメンバーのスキルギャップをより正確に見抜き、適切な指導を行いやすくなります。こうしたスキルは、部下の成長を支援するだけでなく、組織全体に「継続的な成長文化」を根づかせることにもつながります。毎日のやりとりが、成長のチャンスに変わるのです。
では、フィードバックが自然に飛び交う職場をつくるには、どうすればよいのでしょうか。
そのために必要なのは、主に以下の3つの支援です。
フィードバックが根づく職場をつくるために——組織とリーダーにできること

定期的なフィードバックを当たり前にする(評価面談の時だけにしない)

マネジャー向けに対話スキルの
トレーニング機会を提供する

パーソナリティツールを活用して、
コミュニケーションスタイルの違いを理解する
建設的な対立が、職場の健全な成長を導く理由
対立に直面するのは、誰にとっても簡単なことではありません。特に内向的な人にとっては、不安やストレスと結びついてしまい、避けたいと感じることも多いでしょう。しかし、建設的に対立を乗り越える力は、信頼を築き、組織に新たな発見をもたらし、パフォーマンスを高めるために不可欠なスキルです。対立そのものは悪ではなく、明確かつ敬意をもって向き合うことで、むしろ信頼関係を深める機会にもなります。
当社の調査結果によれば、心理的安全性が比較的高い職場環境であっても、対立は依然として繊細で複雑な課題です。多くの従業員が「意見の違いを表明することには抵抗がない」と感じている一方で、「実際に対立に向き合うのは難しい」と答えた人が約9割に上りました。その背景には、「自分がどう見られるか」に対する不安があるようです。対立の精神的負荷は大きく、職場外でも思い悩んだり、身体的な不調として表れることも少なくありません。
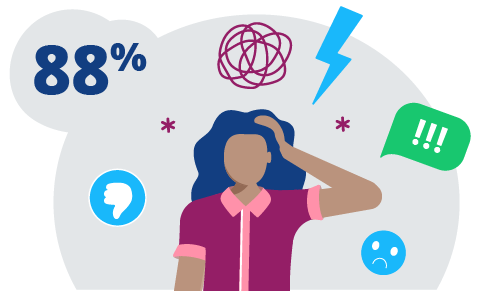
88%の人が「職場での対立に向き合うのは難しい」と回答
対立に取り組むかどうかは、信頼関係の質に大きく左右されます。互いに敬意と理解があり、信頼が築かれている関係性においては、困難なテーマにも向き合いやすい傾向が見られました。
また、対立時のコミュニケーションのスタイルも一筋縄ではいきません。多くの従業員が「率直で即時的なフィードバック」を望む一方で、「一度立ち止まって内省する時間」や「予定された場での対話」を好む人も多数います。これは、「緊急性」と「感情の準備」の間で揺れる葛藤を浮き彫りにしています。マネジャー層は一般的に対立への対応に自信を持っており、特に管理職にある場合はその傾向が強いものの、それでも関係性の力学によって態度や行動が左右されることがあります。
希望が持てるのは、対立にうまく対処できた場合、関係性が強まりチームとしての成果も向上するという点です。特に、「適切な線引き(バウンダリー)」や「本音で感情を表現できる環境」が整っている職場では、その効果が顕著に表れます。

68%の人が「対立を乗り越えたことで、より良い成果を出せた」と回答
エンパワーメント再考:従業員のポテンシャルを「行動」へと変えるには
私たちが明らかにしたのは、従業員をエンパワーするとは、ただ「自信を持たせる」ことではありません。本当に重要なのは、彼らが自ら行動を起こせる環境や条件を整えることです。
多くの従業員が「エンパワーされている」と感じている一方で、実際に自発的な行動に移せている人はそれほど多くはありません。このギャップは、「真のエンパワーメント」には善意以上の仕組みや支援が必要であることを示唆しています。
たとえば、柔軟な働き方(特にリモートワーク)は、従業員が自分の業務を自律的にコントロールしているという感覚を育みます。しかし、問題は“働く場所”ではなく、目標がどれだけ明確に伝わっているか、信頼されていると感じられているか、そして重要な意思決定の権限が与えられているかにあるのです。
エンパワーメントは「時間」で育つものではない
「上司と長く働けばエンパワーメントが育まれる」という考え方は、今回の調査結果により疑問視されています。むしろ必要なのは、明快な方針、信頼、そして心理的安全性。この3つが整ってこそ、自律的な行動が可能になります。

意思決定の権限を「本質的に」与えられた人は、そうでない人と比べて2.8倍も自発的に動く傾向がある
行動に“つながらない”エンパワーメントが多すぎる
本当の課題は、エンパワーメントの「感覚」をどう行動に転換するかです。多くの従業員が立ち止まってしまう理由は、やる気がないからではなく、必要な支援が不足しているからです。重要な意思決定の裁量や、行動に必要な情報へのアクセスがなければ、責任を持って動くことはできません。
そのために必要なのが、以下の3つの支援です。
- 認識(Recognition):努力や成果をきちんと見ていること
- 方向性(Direction):目指すべき方向が明示されていること
- 成長機会(Development):学びと成長の機会があること
しかし残念ながら、これらすべてが十分に提供されているとは限らず、多くのマネジャーが対応に苦戦しているのが実態です。
ポテンシャルは「文化」として育むもの
自分の強みを理解している従業員は、成長意欲も高いものです。しかし、組織からの後押しがなければ、その意欲は埋もれてしまいます。エンパワーメントとは、文化や制度、そして日々のやり取りの中に根づかせるべきものです。それがあってこそ、個々人のポテンシャルは「現実の成果」へと結びついていくのです。
エンパワーメントを促進するためにできること
ポテンシャルを“行動”に変えるために、まず以下の3点から始めてみましょう。

明確な方向性を伝える
ゴールや期待値を、曖昧にせず具体的に示すこと

役割と責任を定義する
誰が何を担い、どこまで決定できるのかを明確にすること

目標を効果的に共有する
個人・チーム・組織の目標がどう連動しているかを見える化すること
AI時代の変化をどう乗り越えるか:変革マネジメントの核心とは
現在、多くの組織が絶え間ない変化の渦中にあります。そして、その影響は明らかに職場に表れはじめています。Wileyの調査によれば、従業員の多くが「次々と変わる状況への対応」に追われ、立ち止まる余裕すらなく、ストレスや“変化疲れ”を感じています。
特に厳しい立場に置かれているのが、ミドルマネジャーたちです。彼らは現場のチームをリードしながら、企業の変革戦略にも対応することが求められていますが、そのために必要な支援や情報が十分に得られていないケースも少なくありません。
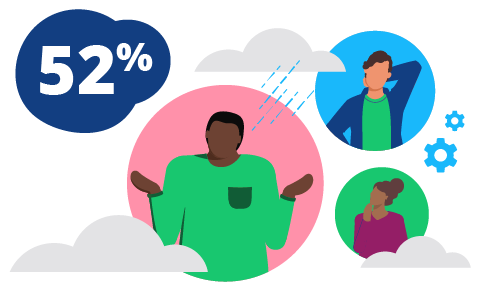
実に52%のミドルマネジャーが「変革をリードする責任を感じている一方で、十分なサポートが得られていない」と回答
従業員が求めているのは、決して難しいことではありません。必要なのは「明確で一貫したコミュニケーション」です。変化に抵抗しているわけではなく、「指針が見えない」「通常業務と変革対応の両立に苦しんでいる」ことが、変化推進を難しくしているのです。
こうした状況に追い打ちをかけるように、AIという新たな要素が加わり始めています。従業員の多くは、AIツールの活用に対して前向きであり、好奇心や期待感も持っています。しかしながら、AIに関する組織内の方針やトレーニング環境が整っていないため、「活用したくてもどうすればよいか分からない」と感じている人も多いのです。

68%の人が「AIに対して好奇心や期待を感じている」と回答する一方で、実際に適切な研修や運用方針を受けている人はごくわずか
このような変化の時代に、組織が本当に必要としているのは、AIの導入や業務改革そのものではなく、「それを支える文化」と「変化をマネジメントする力」です。特にミドルマネジャーの力を信じ、彼らを支援する仕組みを整えることが欠かせません。
明確な言葉で伝えること。現場との信頼関係を築くこと。そして、変化に対応しながらも、人と組織の健全さを保てるような「変化のインフラ」を築くこと。それが、AI時代の変化を乗り越えるための鍵となります。
なぜ多くの従業員が「充実していない」のか──リーダーにできることとは
今日の職場において、モチベーションは大きなプレッシャーにさらされています。パンデミック以前の働き方への回帰が進み、出社時間の増加や業務負荷の拡大、テクノロジーの急速な導入が進む中で、多くの従業員は「自分にとってのメリットは何なのか?」という問いを投げかけています。
リーダー層からは前向きなメッセージが発信されているものの、現場の実情は異なります。ストレスの増大、裁量権の低下、信頼関係の希薄化──こうした要素が重なり、多くの従業員のモチベーションは目に見えて低下しています。
モチベーションは孤立して存在するものではなく、ストレスや組織文化と密接に関わっています。そして現在、そのバランスは大きく崩れているのです。
Wiley社の最新調査によれば、「高いモチベーション」と「適度なストレス」という理想的な状態にある従業員は、わずか17%に過ぎません。それ以外の大多数は、燃え尽きる寸前か、すでに意欲を失っている状態にあります。なかでも特にリスクが高いのが「中堅層の社員」です。彼らはチームの中核を担う存在でありながら、過剰に業務を抱え、十分なサポートが得られていないのが実情です。その影響は、パフォーマンスや定着率の低下という形で現れています。

「高いモチベーション」と「適度なストレス」という理想的な状態にある従業員は、わずか17%
モチベーションは “成果” を生む原動力
組織が人材の潜在能力を最大限に引き出したいと考えるならば、モチベーションは“優先順位の上位”に据えるべきテーマです。それは単なる「やる気」ではなく、「成果を生む力」なのです。モチベーションの高い従業員は、生産性が高く、創造性に富み、困難に対しても回復力を発揮します。
この状態を実現するために、リーダーには意図を持った行動が求められます。
- マネジャーの支援とトレーニング
- 中堅層への継続的な投資
- 強固でつながりのあるチームづくり
加えて、明確なコミュニケーション、継続的なフィードバック、リアルタイムでのエンゲージメントツールの活用によって、従業員の“今の状態”を正確に把握することが鍵となります。
結論はシンプルです。人が「見られ、支えられ、エネルギーを得ている」と感じたとき、その人は力を発揮し、ビジネスも成長するのです。
今すぐリーダーができること
モチベーションを高める3つのアクション

管理職にトレーニング機会を提供する

中堅層をサポートする

チームの一体感を育む
今回の調査を通じて、未来の働き方は「組織として何をするか」だけではなく、「人と人がどうつながり、対話し、協働するか」にかかっていることが、あらためて浮き彫りになりました。5つの調査を通じて一貫しているメッセージは、「心理的安全性」「信頼」「明確な方向づけ」といった“人”の側面への投資は、単なる理想論ではなく、戦略的に不可欠な施策であるということです。
このような土台を整えることで、組織は変化を乗り越えるだけでなく、その変化を糧に成長することができます。人々が「見てくれている」「支えられている」「力を発揮できている」と感じられる文化を育てること――それこそが、先行きが不透明な時代においても、持続可能なパフォーマンスを引き出す鍵になるのです。
原文:Performance Starts with People: Unlocking the Human Drivers of Workplace Success
執筆: Janelle Beck, Senior Copy Editor & Tracey Carney EdD, Research Manager
出典:WILEY Workplace Intelligence|Everything DiSC®(2025年10月24日公開)
◆ WILEY Workplace Intelligence 翻訳記事一覧はこちら
HRDとWiley社のパートナーシップについて
HRDは、米国Wiley社と日本国内における独占販売契約を締結しており、同社が提供する各種アセスメントの日本語版開発および総販売代理権を保有しています。
現在、日本では主に以下の4つのアセスメントを提供しております:
- Everything DiSC®:対人関係と行動傾向を可視化し、組織内のコミュニケーションを促進
- ProfileXT®:職務適性を測定し、採用・配置・育成の精度を高める統合型アセスメント
- CheckPoint 360°™:リーダーの現状と課題を多面的に捉える360度フィードバックツール
- Organizational Alignment Survey:組織の一体感・方向性の共有度合いを測定するサーベイ
またHRDでは、Wiley社からの最新の調査レポートやグローバル動向を継続的にキャッチアップし、日本のビジネス現場に向けて発信・解説する取り組みも行っています。アセスメントの活用にとどまらず、人的資本経営・組織開発の最前線を共有し続けることが、私たちの使命の一つです。
※日本語版以外のご提供も当社にて可能です。詳しくはお問い合わせください。
※当社はWiley社より「2024 Platinum Award Winner」を獲得しています。本アワードは、全世界のパートナー企業のうち上位1%のみに贈られる名誉ある賞です。
We are proud to have received the “2024 Platinum Award” from Wiley. This prestigious honor is awarded to only the top 1% of Wiley’s partner organizations worldwide.
※本記事の著作権は米国Wiley社が保有しています。
※記事の内容、画像、図表などの無断転載・無断使用を固く禁じます。引用される場合は、出典を明記の上、適切な範囲でご使用ください。
Copyright Notice
※This article is copyrighted by John Wiley & Sons, Inc.
※Unauthorized reproduction, use, or redistribution of any part of this article—including text, images, or diagrams—is strictly prohibited. When quoting, please clearly indicate the source and ensure usage is within appropriate and fair limits.
2025年10月29日
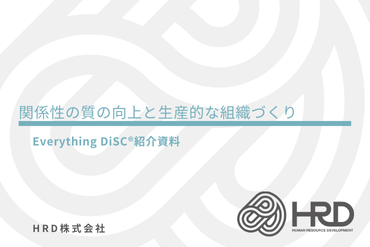
Everything DiSC®紹介資料
本資料では、Everything DiSC®がもたらす体験や対人関係についての尺度、組織カルチャーの共通言語となる特徴についてご説明し、併せて学術的背景、DiSC®理論概要、レポート詳細、活用事例などをご紹介しています。