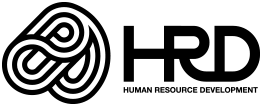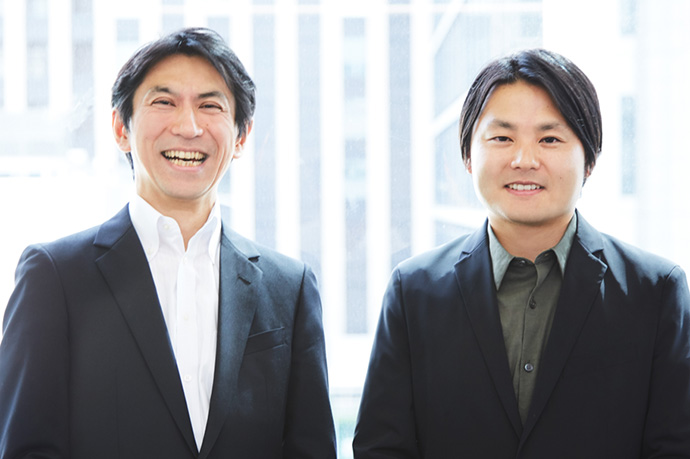「人が人と、よりよく関わるために」
──パーソナリティ心理学で職場を変える
聴き手:金沢シーサイドFM 北島 勇太 氏
2025年9月2日放送の金沢シーサイドFM『社長!あなたの会社教えてください。』に、HRD株式会社 代表取締役の韮原祐介が出演。パーソナリティ心理学に基づくHRDのユニークなアプローチや、これまでの歩み、そして「よりよい未来を後押ししたい」という想いについて語りました。
HRD株式会社とはどんな会社?
――まずは、HRD株式会社について教えてください。
韮原:少し分かりづらいのですが、私たちは「パーソナリティ心理学」を活用して、人がよりよく働ける職場環境づくりを支援している会社です。具体的には、職場における一人ひとりの個性や性格の違いを可視化し、強みを活かし合えるチームづくりや、上司部下の関係改善、エンゲージメント向上といった支援を行っています。
企業研修やコンサルティングを通じて、「人と人とがどう関わると良いか」という実践知を届けている、と言えるかもしれません。
パーソナリティ心理学が生む現場の変化
――具体的にはどのような効果があるのでしょう?
韮原:例えば、とあるハイブランドの店舗では、スタッフ同士の関係性が店舗の雰囲気を左右し、それが売上にも直結します。パーソナリティの理解を通じて、スタッフ間のチームワークが良くなり、結果的に業績が上がるというケースもあります。
また、お客様のパーソナリティを予測し、心地よい接客をすることで売上が伸びることもあります。社内では離職率の低下やエンゲージメントの向上など、「人が人を理解すること」で生まれる効果は多岐にわたります。
30年の歩みとグローバルなネットワーク
――HRDの強みは、長年の蓄積にもあるのですね。
韮原:おかげさまで創業から30年以上、2000を超える企業や官公庁などに導入いただいています。また、私たちが扱っているアセスメントツールはアメリカ発祥のもので、全世界のパートナーネットワークと知見を共有しながら、日本語版として提供しています。
「性格診断」とは何が違うのか?
――最近流行っている「16タイプ診断」などとは違うのでしょうか?
韮原:似ている分野ですが、決定的な違いがあります。16タイプ診断は「内向型か外交型か」といったゼロイチで分類する“類型論”がベースです。一方、私たちのアセスメントは、どちらの傾向も持っている前提で、その強さを1〜10のスケールで数値化します。 「あなたも私も外交型ですね」ではなく、「あなたの外交性は7、自分は4」などと比較できるので、実際の関係性や対応に役立ちます。人との違いを理解し、それに合わせた関わり方を見つける実用性の高さが特徴です。
人を「丸裸」にする? いえ、そうじゃない
――韮原さん、人を見ただけでわかってしまうことも?
韮原:よく言われますが、そんなことはありません(笑)。その人がその場に求められる行動をしていることもあるので、見た目だけで判断するのは危険です。ただ、私は子どもの頃から父(創業者)の講演テープを聞いて育ったこともあり、性格の違いや行動の背景には敏感だったかもしれません。
でも結局、特別な能力ではなく、誰でも“普通の使い方”で相手とのよりよい関わり方が見つけられる──それが我々のアセスメントの価値だと思っています。
ミッションではなく「想い」を大切に
――会社としての思いや、モチベーションを教えてください。
韮原:私たちは「ミッション」という言葉をあえて使っていません。ミッションという言葉は宗教や軍事の文脈に由来し、強い命令や使命感が内在しています。でも、私たちが大切にしたいのは、1人ひとりが持つ“自然な動機”なんです。
「人がその動機に沿って働ける」「希望を持てるような支援ができる」。そんな組織でありたいと思っています。
HRDが目指すのは、主役が“お客様”である支援
韮原:私たちが目指しているのは、HRD自身が主役になることではありません。お客様一人ひとりの希望や可能性を引き出し、より良い未来への一歩を後押しすること──それが私たちの役割だと考えています。
「こうあるべきだ」と押しつけるのではなく、「こういう可能性もあるかもしれない」と気づいてもらえるような関わり方をしていきたい。そんな姿勢で、お客様と向き合っています。
■代表エッセイ「Leadership in Chaos〜”こころ”と”そしき”の交差点 〜」記事一覧はこちら
■「韮原祐介の匠たちの育成哲学」 連載記事はこちら
■代表メッセージはこちら
2025年09月03日