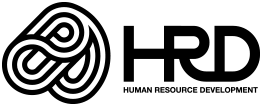「精神論」は時代に合わない――相撲部屋の親方と考える感情論ではなく言語化された指導
韮原祐介の匠たちの育成哲学 第6回
ゲスト:九重 龍二 氏
(九重部屋・第十四代九重親方)
HRD株式会社代表・韮原祐介が、“人を育てる立場”にある、各界のリーダーやトップをゲストに迎え、人材育成と自己成長をテーマに語り合う当連載。今回は名門・九重部屋の第十四代九重親方こと九重龍二氏と「精神論と観察眼」について本音で語り合う――。【雑誌『サイゾー』にて連載中:2026年2月号より転載】
対談者のご紹介

韮原祐介(にらはら・ゆうすけ)
HRD株式会社 代表取締役
1983年、千葉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、アクセンチュア、ブレインパッドにて戦略策定、組織改革、AI・データ活用などのさまざまなコンサルティングプロジェクトに従事。現在は、HRD株式会社にてパーソナリティ心理学を活用してクライアント企業の人材と組織の課題解決を支援。東京大学非常勤講師、東進デジタルユニバーシティ講師などを歴任。著書に『いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本』(インプレス)、『サイバー攻撃への抗体獲得法』(サイゾー)がある。

九重 龍二氏(ここのえ・りゅうじ)
九重部屋・第十四代九重親方
1976年、大分県生まれ。元大関・千代大海。中学卒業後、大横綱・千代の富士が親方を務める九重部屋に入門。92年に初土俵を踏み、99年に大関へ昇進。通算成績は771勝528敗115休。幕内最高優勝3回。大関在位65場所という記録は、大相撲の長い歴史の中でも歴代1位タイの大記録。2010年に現役を引退。引退後は年寄「佐ノ山」を襲名し、九重部屋付の親方として後進の指導にあたる。16年、師匠・十三代九重の逝去に伴い、第十四代九重を襲名し、九重部屋を継承した。

韮原祐介(以下、韮原):大関在位65場所は歴代1位タイで、幕内最高優勝を3度果たした2000年代を代表する大関・千代大海関。現在は九重龍二として、師匠である大横綱・千代の富士関(十三代九重)の跡を継ぎ、名門・九重部屋の第十四代九重親方として弟子たちの指導に心血を注いでいます。「どういう関係?」と思われるかもしれませんが、この連載の第1回に登場したアーティストの高橋理子さんが九重部屋の仕着せ(浴衣)をデザインしているご縁で、今回ご一緒させていただくことができました。改めて、親方が力士になるまでの経緯を教えてもらえますか?
九重龍二(以下、九重):僕は中学に上がる頃には体重が100~ 110キロ、身長は172センチほどと、小学生の頃から頭ひとつ分大きかった。そのため、小学4年生の頃からいろいろな相撲部屋がスカウトに来てくれていましたが、すべて門前払いにしていました。
韮原:しかし、16 歳のときにお母様に「力士になれ!」と言われたことが転機となったそうですね。
九重:そう。そして、実は九重親方だけはスカウトに来ませんでした。でも当時最強の横綱といえば千代の富士、『キン肉マン』の「ウルフマン(=リキシマン)」のモデルというのも知っていて、入門するなら強い人の部屋に行きたいという思いから、九重部屋に入門しました。
韮原:1992年に初土俵を踏まれますが、Netflixのオリジナルドラマ『サンクチュアリ ー聖域ー 』などでも描かれているように、相撲界の下積み生活には壮絶な印象があります。稽古や住み込み生活の中で、特に大変だった記憶はありますか?
九重:もう、すべてが過酷でした。息をするのもキツいくらいです。当然すべてのことを自分でやらなければけない。しかも、50人近い兄弟子がいるので、その先輩たちの身の回りの世話もする。米も炊いて、おかずも50人分作って、食器は数百枚洗う。洗濯もする。そんなさまざまな用事をしていると、寝るのは2時半になります。朝の稽古は4時半から始まるのに。
韮原:えっ……。途中で昼寝など休憩はできたんですか?
九重:そんな時間はありません。常に「死ぬんじゃないか」と思うくらいきつかった。だからこそ、「早
く強くならなくては、この世界では生きていけない」と感じていました。2カ月に1回ある本場所が、ものすごく遠くに感じられた。「毎月、場所があればいいのに」と思っていたくらいです。

常にプラスアルファを意識 目標は初めから大きく持つ
韮原:どの業界でも、入りたての頃は苦労するものですが、相撲界はそれとは比べものにならないほど過酷に思えます。そんな生活が続くと逃げ出す新米力士もいると聞きますが、親方の場合はどうでしたか?
九重:僕は師匠にすべてを託していましたし、一度自身で決めたことは曲げない。さらには、師匠に対して一度も「できません」と言ったこともありません。「やれ」と言われたことは必ずやりきりました。僕が人と違うと自負していたところは、言われたこと以上に〝プラスアルファの努力〟をしていたことだと思います。
韮原:ただでさえ過酷な状況にもかかわらず、何が親方をそうさせたのでしょうか。
九重:人と同じことをしていても、番付を上っていくことはできないと客観的に認識していました。みんなが腕立て伏せを100回やるなら、僕は500回やる。300回ならば、僕は1000回。常にそのように実践していました。それを師匠も見てくれていたし、理解もしてくれていました。
韮原:衣食住を共にする相撲部屋という組織は、一般的な企業よりも人と人との距離が近いかと思います。タフで上下関係が厳しい分、そこで築かれる師弟関係や絆は、より強固なものになりますよね。そうした環境の中で、他の弟子たちよりも多くの努力をすることが自身を成長させる道なんですね。
九重:僕も自分自身への限界への挑戦という意識だけではなく、師匠に認めてもらいたいという気持ちもあったので、「今日は800回でいいか」なんてことは絶対にありませんでした。1000回できたら、次は1200回。常に〝プラスアルファ〟を意識していたんです。
韮原:相撲もスポーツもビジネスも、高いパフォーマンスを得るには、目標設定が大変重要かと思います。親方の場合はいかがでしたか?
九重:僕の目標は入門当初から横綱でした。序ノ口で迎えた最初のデビュー場所で、全勝優勝したとき、インタビューでNHK(当時)の吉田賢アナウンサーから「将来の目標は?」と聞かれたので、「横綱です」と答えました。そのときは「序ノ口のくせに大きなことを言って」と、笑いものにされました。ですが、僕は「やるならてっぺん」という性分だったんです。
韮原:最初から頂点を目指していたからこそ、他の力士よりも厳しく自分を律して稽古に励んでこられたのでしょうね。少し野暮な質問かもしれませんが、ご自身の中で「この時期が一番輝いていた」と思うのはいつ頃でしょうか?
九重:全盛期で言うと、やはり二度目の幕内優勝を果たした2002年。26歳から28歳くらいの頃ですね。入門してから10年ちょっと経ち、ただ活発だったというだけではなく、「大人というのはこういう話し方をするんだな」や「一流の人とはこんな会話や食事をするんだな」といったことまで理解できるようになってきて、全てが整ってきていたと感じていた時期でした。
韮原:心技体が備わり、相撲の世界でも外の世界でも一流になっていかれたのがその頃だったんですね。
九重:関取になったのは19歳。しかしながら、そのときはまだ〝一人前〟という感覚はなかったですね。22歳で初優勝して大関になるまでは、ただただがむしゃらでした。常に殺気立っていて、周りを見渡し客観的に自己評価している場合ではなかったですね。
根性と精神論は通用しない 重要なのは観察眼と気配り
韮原:そんな厳しいライバルたちとの戦いを経て、現在は親方、つまり指導者として人材育成に取り組まれています。昔と今では、教え方もだいぶ変わってきたと伺いましたが、どのように新たな指導法を見出していかれたのでしょうか?

九重:もう、それは本当に〝ミリ単位〟の精度での調整です。僕は引退後、いきなり師匠になったわけではなく、年寄「佐ノ山」としての期間が8年ほどありました。その間は、師匠の右腕として、ずっと稽古の指導をしていました。その当時は、自分が体で教えていましたが、今は口頭で伝えなければならない。それが、なんと難しいことか……。肌を合わせて稽古をつけるほうが、ずっとハードルが低いです。
韮原:やはり言葉だけで伝えることには限りがあるものですよね。
九重:理屈、要素、技術……。それらすべてを言語化して指導するというのは、本当に難しいんです。基本的には冷静に理性で対応すべきなのですが、ときに感情を全面に出して、「お前ら、この野郎!」と叱ることもあります。でも、それもとても重要なんです。なぜなら、相手も「この人は本気で向き合ってくれているんだ」と感じることができるから。決して、罵るわけではなく、心の底から対峙するということです。
韮原:それも、親方が、弟子と相撲を愛しているからこそですね。九重部屋のお弟子さんたちも、親方が厳しいことを仰る裏にある想いを理解されているわけですね。
九重:正直、本当にキレてしまって、反省することもあります。でも、翌日以降、弟子たちの姿勢や態度が良くなっていたりすると、そのような対応にも意味があるんだなと思えるんですよね。
韮原:とはいえ、恐れの指導だけを連発しても効果的ではないですよね。なかなか「叱る」だけで成長は起きないものかと。どのように力士たちを鼓舞しているんですか?
九重:まずは信頼関係を築くこと。その上で本人が心の底から頑張ろうと思えるような状況を生み出し、能動的に行動できるスイッチをいれることが大事なんです。かつては、「お前は才能がないから帰れ!」と叱られることもありました。そう言われても、「唇を噛んででもがんばる!」という根性や精神論が美徳とされていた。でも今は、そういう言葉は叱咤激励ではなく「本気で否定された」と受け取られてしまう。
韮原:あらゆる指導・教育の現場で、そうした指導は選ばれなくなってきていますよね。ビジネス界もそうですが相撲界も人材不足、つまり力士としての入門希望者の数が随分減ってきたと聞いています。限られた数の力士たちの中で、いかに彼らを成長に導くかがより重要になってきているものと感じます。
九重:僕たちが学んできた、〝精神論で乗り越えろ〟というやり方は、今の相撲界においても合わなくなってきているんです。だからこそ、指導者は観察眼を養って、弟子たち一人ひとりの変化を取りこぼさないようにしなければなりません。
韮原:なるほど。企業人事の世界では、メンバーシップ型からジョブ型へと進んできましたが、これからは「パーソナライズ型」だと思っています。それを実現するには、会社が用意した制度だけでは不十分で、各現場の管理者や同僚が、個々に合わせた関係性づくりをしていく必要があります。まさに親方がやっていらっしゃるように、毎日弟子の顔つきから状態を予想し、それに応じて対応を変える……。親方は私が企業人事の現場で今後必要だと考えるマネジメントをまさに実践されていますね。
九重:昔は「根性がないと土俵に上がる資格はない」と教えられました。実際、朝4時半に稽古場に降りるには、それ相応の気合いが必要。ダラダラとはできませんし、気力がないとやっていられません。そこで経験した厳しさは、今でも体に染み付いています。だから、今の弟子たちにも同じように指導したい気持ちはありますが、精神論や根性は、技術には結びつかないのも事実です。その精神を伝えられないという歯がゆさがある一方で、僕が経験したことをうまく噛み砕いて、弟子たちがどうすれば「正しく相撲道を歩めるか」を考えることが、今の僕の教育方針です。
掲載元:[人材育成イノベーター]韮原祐介の匠たちの育成哲学(サイゾー 2026年2月号掲載)
古寺雄大|構成・増永彩子|写真
▶ 対談記事一覧はこちら
2026年01月20日