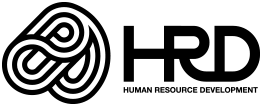「やり直し」こそが仕事の本質――彫刻家と考える試行錯誤を繰り返すことの重要性
韮原祐介の匠たちの育成哲学 第5回
ゲスト:青木 邦眞 氏
(彫刻家・埼玉県新座総合技術高校 デザイン科教諭)
HRD株式会社代表・韮原祐介が、“人を育てる立場”にある、各界のリーダーやトップをゲストに迎え、人材育成と自己成長をテーマに語り合う当連載。今回は「ロエベ財団 クラフトプライズ2025」大賞受賞者である青木邦眞氏と「伝統と革新」について本音で語り合う――。【雑誌『サイゾー』にて連載中:2025年11月号より転載】
対談者のご紹介
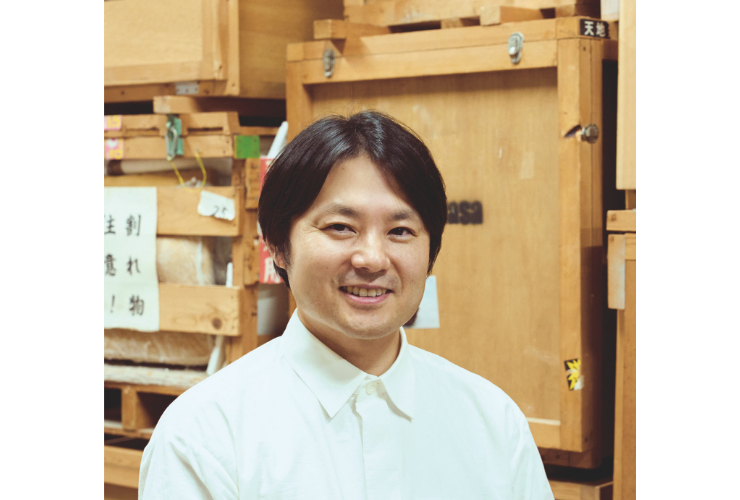
韮原祐介(にらはら・ゆうすけ)
HRD株式会社 代表取締役
1983年、千葉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、アクセンチュア、ブレインパッドにて戦略策定、組織改革、AI・データ活用などのさまざまなコンサルティングプロジェクトに従事。現在は、HRD株式会社にてパーソナリティ心理学を活用してクライアント企業の人材と組織の課題解決を支援。東京大学非常勤講師、東進デジタルユニバーシティ講師などを歴任。著書に『いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本』(インプレス)、『サイバー攻撃への抗体獲得法』(サイゾー)がある。

青木 邦眞氏(あおき・くにまさ)
彫刻家・埼玉県新座総合技術高校 デザイン科教諭
1963年、埼玉県川口市生まれ。武蔵野美術大学彫刻科を卒業後、89年に同大学大学院を修了。以後、美術予備校講師や高等学校の非常勤講師を経て埼玉県立新座総合技術高校・デザイン科教諭として32年間にわたり勤務する。彫刻家としても活動を続け、2011年には神戸ビエンナーレ現代陶芸大賞、23年には日本芸術センター彫刻コンクール金賞を受賞。25年には、「ロエベ財団 クラフトプライズ2025」にて大賞を受賞する。作品は兵庫陶芸美術館、日本芸術会館、川口市立美術館、ロエベ財団(スペイン)など、国内外に収蔵されている。

韮原祐介(以下、韮原):まずは今回の受賞おめでとうございます!スペインを代表するハイブランドのロエベは、皮革工房としての出発点を持ち、職人技を重んじるものづくりがブランドの特徴です。クラフトマンシップへの強いこだわりを持ち、創業者一族の4代目にあたるエンリケ・ロエベ・リンチ氏は、1988年に詩や舞踊、写真、アート&クラフトといった分野の遺産を守るため、「ロエベ財団」を設立、2016年には「ロエベ財団 クラフトプライズ」を創設しました。これは陶芸、木工、ガラス、金属、織物、ジュエリーなど幅広いジャンルを対象に、芸術性とクラフトマンシップに優れた革新的な作品をたたえる、年に一度の国際賞です。その25年の大賞を受賞したのが、今回のゲストの青木邦眞さんです。青木さんは埼玉県立新座総合技術高校のデザイン科教諭で、生徒の教育指導の日々の傍ら、彫刻家として自身の作品作りをしています。
青木邦眞(以下、青木):「ロエベ財団 クラフトプライズ2025」に応募したのは24年の10月頃。インターネットで受賞作品を見かけて、「ロエベの賞があるんだ」と知りました。
韮原:青木さんは11年に神戸ビエンナーレ現代陶芸大賞、23年には日本芸術センター彫刻コンクールで金賞を受賞されていますが、これまでも海外展への出展経験はあったのでしょうか?
青木:出したい気持ちはありましたが、なかなか情報が得られなかったんです。というのも、私は英語が苦手で(笑)。それでもネットでいくつか候補を見つけて、「とにかく挑戦してみよう」と思い、「ロエベ財団 クラフトプライズ」に応募しました。
韮原:そして見事、大賞を受賞されたのですね。
青木:応募から約3カ月後、25年1月にロエベ財団の日本支部から連絡がありました。ちょうど応募したことを忘れていた時期で、電話がかかってきたときも「すみません、今から職員会なので」と一度切ってしまったんです(笑)。その後かけ直すと、「ファイナリストに選ばれました」と言われてびっくりしました。インスタグラムを開いてみたら、フォロワーが急に増えていて、「これはすごいことになってきたな」と実感しました。

テラコッタによる生命感あふれる造形を特徴とし、日本の縄文式土器に見られる「ひも作り」技法で一層ずつ築く。時に形を潰し歪ませ、意図を超えた現象を誘発し作品が自立する瞬間を引き出す。自然界の小さな力が時を経て形を生む現象に着想。(青木氏より提供)
韮原:受賞作は、粘土で制作された《Realm of Living Things19》(2024年)です。「realm(レルム)」には「領域」という意味があります。
青木:日本語で言えば「生きものの領域」という作品名になります。私にとって〝領域〟とは、生命が吹き込れて物質が生き物になっていくような、そんな変化の過程を指しています。作品に生命が宿る瞬間、つまり〝生き物の領域〟に達することが、自分のテーマであり、目指している方向性です。
韮原:今年は133の国と地域から、昨年を上回る4600点以上の応募があり、ファイナリストに選ばれたのは30人。その中のひとりが青木さんだったわけですね。
青木:マドリードのティッセン=ボルネミッサ国立美術館で展示されることが決まり、「5月28日に来てください」と連絡がありました。ファイナリストは受賞に関係なく全員が招待されており、当日になって初めて大賞受賞者が発表される仕組みでした。
韮原:ハリウッド俳優のメグ・ライアンや、映画監督のペドロ・アルモドバルといった豪華な面々がプレゼンターとして登場したと聞いています。
青木:昨年の大賞はセラミック作品だったので、同じ素材を使用した自分が今回は選ばれることはないだろうと思っていました。だからこそ、パーティーも授賞式も純粋に楽しむつもりで参加していたんです。ところが突然、大賞受賞者として自分の名前が呼ばれました。何が起きたのかわからず戸惑いながらステージに立ち、スピーチを求められたものの、準備していなかったので英語では「Thank you」としか言えず……(笑)。そのあと、すぐに別室に案内され、メディアのインタビューを受けました。まったく予想していなかった展開で、本当に驚きました。
世界が認めた「伝統と革新」縄文土器から工芸に至るまで
韮原:審査員は青木さんの作品のどのような点を評価されたのでしょうか?
青木:「伝統と革新」の両方が作品に表れていたからだと思います。私の作品には、古くから使われている「紐作り」という技法が含まれています。これは縄文式土器にも見られる伝統的な手法で、陶器を作る人であれば誰もが一度は試すような基本的な技法でもあります。ただ私は、完成度を求めるのではなく、割れやゆがみといった〝失敗〟とされがちな要素も積極的に取り入れています。さらに、粘土の端をそのまま生かすなど、通常なら整える部分をあえて残している。そうした点が評価されたのかもしれません。
韮原:紐作りとは、紐状にした粘土を巻くようにして積み上げ、継ぎ目を滑らかに整えて成形する、手びねりの基本的な技法のひとつですね。
青木:だいたい直径5ミリほどの紐を作って、上から押さえながら積んでいきます。この方法は縄文時代にも使われており、弥生式土器などでも同様に紐状の粘土を積み上げて成形します。私自身は、「積み上げた紐を潰したときにできる表面には手を加えない」というルールを設けています。通常は、ヒビやゆがみがあると表面をならして修正しますよね。でも私は、外側には手を加えず、内側だけを整えるようにしています。
韮原:それはなぜでしょうか?
青木:そうすることで、潰すときの力の痕跡や、積み上げてきた時間、その行為そのものが表面に残るんです。それを消してしまうと、積み重ねてきたものがすべて無になってしまうような気がして。だからこそ、あえてそのまま残すという作り方を、自分の中でひとつのルールとして続けています。
韮原:まさに、「伝統と革新」。それこそがロエベの審査員に伝わったポイントだったのでしょう。

(青木氏より提供)
青木:工芸はアートでもあり、「用途があるかどうか」ではなく、素材そのものの質感をどう生かすかが重要だと感じています。その考えが、評価につながったのではないでしょうか。また、単に「伝統を受け継ぐ」だけでなく、現代の感覚を通して、どのように革新的な表現を実現するか……。今回ファイナリストに選ばれた30名の作品にも、そうした姿勢が共通していたように感じます。
韮原:制作にはどれくらいの期間がかかったのでしょうか?
青木:3カ月ほどです。その間、粘土をひとつずつ積み上げていくのですが、粘土は乾いてしまうので、常にフードラップを巻いて保護しながら進めます。ただし、下からは少しずつ乾いていくため、乾くまで上に積むことができない。乾燥の進み具合を見ながら、慎重に作業を続けます。途中まで積んだら、上から思いきりグニャっと押し潰すんです。
韮原:ユニークな技法ですよね。
青木:これはとても重要なプロセスで、「作品と自分との距離感を保つ」ために行っています。作品というのは、例えばエスキースを描いて「こういう形にする」と決めてしまうと、そこからはただの作業になってしまいがちです。自分の作品であっても、あまりに手が入りすぎると、作業に没入して距離を失ってしまう。そこで、あえて作品を壊したり潰したりすることで、一度距離を置くんです。すると、作品が自分から少し離れる感覚がある。そこからまた積み上げていくと、また近づく。でもまた潰して遠ざける。その繰り返しの中で、最終的に「ちょうどいい距離感」が保たれたとき、作品が自立し、本当の意味で〝作品になる〟気がしています。
再提出ばかりさせる先生?「やり直すこと」の重要性
韮原:「作品を作っている」というより、「作品を生み出している」という感覚ですね。初めて青木さんの作品に触れたとき、優しさとぬくもりをまとった作品のように見え、心を打たれました。作品から、「きっと深い愛情を持った方なんだろうな」と、自然に感じられます。ところで、大賞を受賞されたあと、生徒のみなさんの反応はいかがでしたか?
青木:ちょうど体育祭の時期だったので、私の等身大パネルを作ってくれたんですよ(笑)。それから、卒業生たちからもメールやインスタグラムのメッセージをたくさんいただきました。
韮原:実はこの連載の第1回に登場した高橋理子さんは、青木さんの教え子なんです。彼女は「青木先生がいなかったら、東京藝術大学には進学していなかった」とおっしゃっていました。普段、生徒のみなさんにはどのようなことを教えているのでしょうか?
青木:「さらっと作品を作る」ような教え方はしていません。粘り強くというか、かなりねちっこい指導をしていると思います(笑)。例えば課題では、「1枚描いて終わり」ではなく、「2枚描いて比べてみよう」と教えます。最初の作品には手を入れたり、具体的な指示を出してリメイクさせたりして、〝ビフォーアフター〟を目に見える形にしています。そうして何度も描き直させるので、生徒たちからは「再提出ばかりさせる先生」と思われているかもしれません(笑)。でも、それもデザイン教育のひとつのかたちだと考えています。デザインでは、「一発で完璧な作品ができる」ことなんて、ほとんどありません。むしろ大切なのは、試行錯誤を繰り返すこと、つまりトライアンドエラーの積み重ねです。
韮原:確かに、デザインの現場では一度で「これでOK!」になることはまれですよね。クライアントとのやりとりの中で何度も修正が入り、そのキャッチボールで完成にこぎ着けるようなところもある。だからこそ、「やり直すこと」は、とても実践的ですね。
青木:そうですね。ただ、私もすでに定年を迎えていて、今は再雇用というかたちで勤務しています。せっかく賞もいただいたので、これからは少しずつ個人の制作活動にも力を入れていこうと思っています。
韮原:高校教師としての一区切りのタイミングで、ロエベ財団から大きな賞が届いた。もしかするとアート界が、「のんびり隠居なんてさせないぞ」というプレッシャーをかけてきたのかもしれませんよ。先日も収蔵を検討してアメリカの公立美術館の方々がいらっしゃいましたよね。
青木:まずは、自宅アトリエの整備から……。それが最初の課題ですね。がんばります(笑)。
掲載元:[人材育成イノベーター]韮原祐介の匠たちの育成哲学(サイゾー 2025年11月号掲載)
古寺雄大|構成・増永彩子|写真
▶ 対談記事一覧はこちら
2025年10月21日