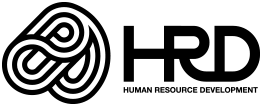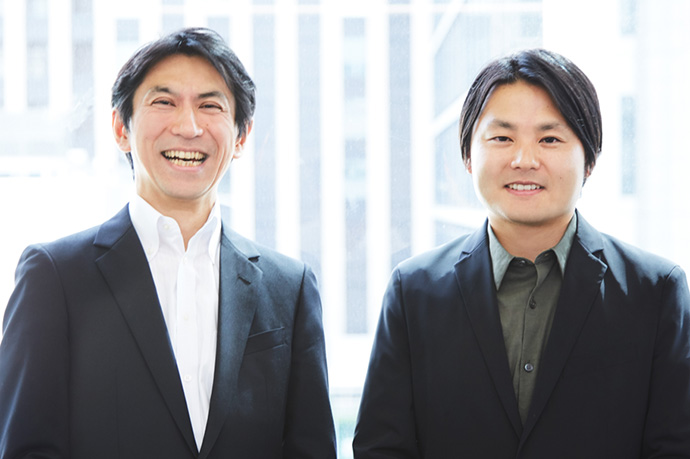一騎当千の人材を生む教育――医療経済学者と考える「再現可能な先人からの教え」
韮原祐介の匠たちの育成哲学 第4回
ゲスト:高久 玲音 氏
(一橋大学経済学研究科教授)
HRD株式会社代表・韮原祐介が、“人を育てる立場”にある、各界のリーダーやトップをゲストに迎え、人材育成と自己成長をテーマに語り合う当連載。今回は医療経済学の専門家である高久玲音氏と「日本の医療の課題」について本音で語り合う――。【雑誌『サイゾー』にて連載中:2025年8月号より転載】
対談者のご紹介

韮原祐介(にらはら・ゆうすけ)
HRD株式会社 代表取締役
1983年、千葉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、アクセンチュア、ブレインパッドにて戦略策定、組織改革、AI・データ活用などのさまざまなコンサルティングプロジェクトに従事。現在は、HRD株式会社にてパーソナリティ心理学を活用してクライアント企業の人材と組織の課題解決を支援。東京大学非常勤講師、東進デジタルユニバーシティなどを歴任。著書に『いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本』(インプレス)、『サイバー攻撃への抗体獲得法』(サイゾー)がある。
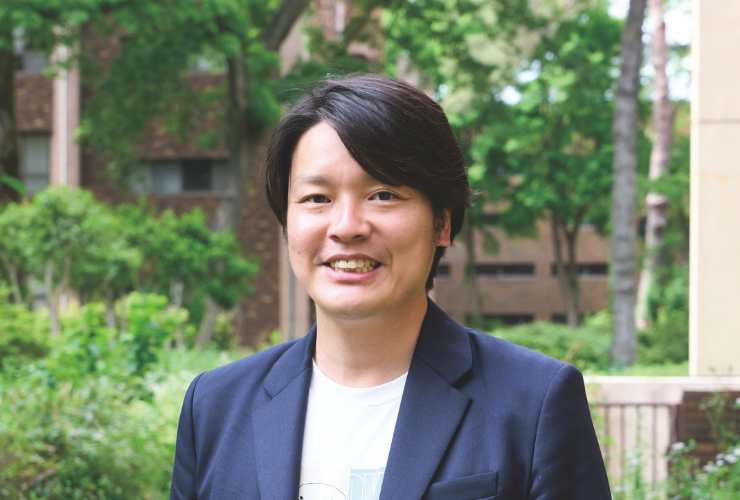
高久 玲音氏(たかく・れお)
一橋大学経済学研究科教授
1984年、横浜市生まれ。2007年に慶應義塾大学商学部を卒業後、09年に同大学大学院商学研究科修士課程を修了。12年に同博士課程を単位取得満期退学。15年に商学博士を取得。日本経済研究センター研究員、医療経済研究機構主任研究員を経て、19年に一橋大学経済学研究科准教授に着任。24年より現職。専門は医療経済学と応用ミクロ計量経済学。全世代型社会保障構築会議構成員、経済財政一体改革推進委員会社会保障ワーキンググループ委員、東京都地域医療構想アドバイザー、厚生労働省行政事業レビュー外部有識者などを歴任。

韮原祐介(以下、韮原):今回のゲスト・高久玲音教授は、政府の社会保障関連の審議会や検討会で委員を務めた慶應義塾大学商学部の権丈善一(けんじょう・よしかず)教授のゼミで先輩後輩の関係です。文字通り机を並べて勉強していました。
高久玲音(以下、高久): 権丈先生は「ニラ(韮原氏)は頭がいいところがあるからな」と言っていましたね。あまり人を褒めない先生だったので、その言葉が印象に残っています。
韮原:まったく記憶にないですね(笑)。さて、高久教授の専門は医療経済学です。まず初めにどのようなことを研究しているのか、教えてもらえますか?
高久:医療経済学というとビジネスに近い話だと思われがちですが、私の専門は政策評価です。医療には年間45兆円もの国家予算がかかっています。これは非常に大きな規模ですが、これまでの政策決定は、医師会や保険者でもある企業の代表など利害関係者のネゴシエーションによって決められてきた面があり、必ずしもデータやエビデンスに基づいた意思決定がされてきたわけではありません。本来、医療全体がどうなっているのか国民にも伝わるように、データを提示しながら政策を決める必要があります。そうでなければ、政策に対するアカウンタビリティ(説明責任)を保つことができません。アカウンタビリティは政府に対する信頼に大きく影響しますし、これが保てないとある種の陰謀論が幅を利かせてしまいます。そうならないように、微力ながら取り組んでいるのが私の専門です。

韮原:高久教授は「コロナ禍の休校が子どもたちに与えた影響」を測定するなど、「健康に関わることなら何でもやる」ということで、とにかくデータをしっかり集めて分析するのが特徴ですよね。
高久:緊急事態宣言発令以降、1回目の休校が終わった3カ月後に、子どもたちへの調査を実施しました。感染症対策は健康を守るために行われますが、その対策自体が非常に不健康である場合もあります。「コロナ」を特別視するのではなく、「健康」全体でさまざまな対策を評価できないかという問題意識から研究を始めました。
韮原:コロナ禍の休校で、子どもたちの健康にはどのような影響がありましたか?
高久:体重の増加や、母親のメンタルヘルスの悪化といった影響が見られました。3年ほど経過した時点では、「修学旅行に行けなかった」といったケースが多く見られたため、そうした経験が子どものメンタルヘルスにどのような影響を与えるかも調べました。大人の旅行はGoToトラベルで補助されたのに、めちゃくちゃです。
韮原:メンタルヘルスはどのように測るのですか?
高久:精神科を受診すると行われるスクリーニングテストと同様の質問票を用います。これは国際的に標準化されており、オンラインでも実施可能です。質問に答えて合計点を出し、その点数が一定以上であれば「軽度のうつ病のリスクがある」といった評価がされます。
既得権益側の医師たち 入試方法をくじ引きに?
韮原:「緊急事態宣言によって感染が減少するのか」といったテーマにも取り組んでいます。
高久:「新型コロナウイルスと病院」についても研究を行いました。当時、「医療が逼迫している」と言われていた一方で、患者をほとんど受け入れていない病院も多く、逼迫していない病院も多かったです。この点については、情報公開請求を各都道府県に行い、病院ごとの受け入れ状況を可視化しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、医師会や医療業界にとって、国民の信頼を高める非常に大きなチャンスだったはずで、国民も医療界に多くを期待していました。実際には頑張った医療機関があった一方で、そうでないところも存在しました。そして、そのような事態に対して、医療業界の「自浄作用」が乏しかったという印象もあります。
韮原:医療ビジネスは、人々の健康に関わる非常に重要なものであることは言うまでもないですが、一方で国の制度に守られた既得権益を持ってもいます。医師会といった形で大きな政治力を持った団体を形成していますし、医師という職業も世襲的側面もありますよね。
高久:昔の医療界には、非常に強い……しばしば強すぎる倫理観と責任感があったと思います。大江健三郎の『ヒロシマ・ノート』(岩波書店)によると、広島に原爆が投下されたとき、現場に残って被爆しながらも治療に当たった医師がいれば、逃げてしまった医師もいたそうです。それに対して、広島市医師会は13年後、被爆生存者である会員に対して、「貴下は原爆当時どこに居られましたか」「貴下は被爆当時、被爆者の救護に従われましたか」とアンケートを取ったそうです。
韮原:つまり、医師会が「まさか逃げなかったよな?」と自主的な検証を行い、それが職業倫理の統制にもなったわけですね。
高久:こうした行動があったからこそ、日本国民は医師に対して強い信頼を持っていた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大時には、医療界全体が身内をかばい合うような雰囲気が強かったのではないかと思います。補助金はもらうのに、発熱外来を設置していることを住民に対して公表すらしない診療所が続出しました。こうしたことが続くと、専門職集団としての信頼は損なわれてしまいます。新型コロナウイルスの感染拡大は、そうした意味でも、日本の医療制度における転換点だったかもしれません。
韮原:医師の話に限った話ではありませんが、国際政治学者のサミュエル・ハンチントン著『分断されるアメリカ』(集英社文庫)では、ハーバードやイェールなどの名門校を出た超エリート層と、いわゆるラストベルトの労働者たちとの間で分断が進み、上位1%が莫大な富を手にし、それ以外の人々は苦しい生活を強いられるという構図が描かれています。それが今のトランプ政権につながるわけですが、日本もそうした分断構造に近づいているように思います。例えば、一般診療所の院長の平均年収は有床で約3400万円、無床で約2600万円という調査があり、日本人全体の平均所得の5~7倍以上あります。もちろん、彼らは努力してその地位を得たのですが、医師の所得は、国民みんなが払う保険料や税金から来ています。分断が進んでいけば社会保障そのものが前提としている「国民全体での支え合い」の意識が失われ、制度そのものが危ぶまれないかと懸念しています。

高久:医師はもちろん素晴らしい職業である一方で、幼い頃から受験戦争を勝ち抜いてきた「勝ち組エリート」の象徴でもあります。医学部に入ると、18歳から医師という閉ざされたコミュニティに属することになり、社会の見え方自体が一般人とは異なるという面もあると思います。だからこそ、専門家組織としての「自律」や「自浄作用」が非常に重要になります。国民の信頼を保ち続けるためには、自らを律する力が求められるのです。
韮原:医学部の入試を「くじ引き」にするというアイデアをお持ちでしたよね。
高久:実際にオランダでは一部でくじ引き制度が採用されています。その背景には、「良い医師」を選ぶ確かな基準を設定することが技術的に困難だということと同時に、「公益に資する職業」においては、「たまたまその職業に就けた」という感覚が重要だという考え方があります。もし「医師になれたのは自分の能力と努力の賜物だ」となってしまうと、他者への共感が薄れ、国民の反感を買いやすくなるのではないでしょうか。完全な実現は難しいかもしれませんが、議論として非常に意義があると思います。「たまたま良い職業に就けた」という感覚を持つこと。それが、医療のように公益性の高い職業には、より強く求められるべきです。
韮原:学生時代からの仲ですが、こんな話をしたのは初めてかもしれませんね。もともと、研究者を目指して権丈ゼミに入ったのですか?
高久:当時はまったくそのようなことは考えていませんでした。ただ、権丈先生の専門が社会保障だったこともあり、先生の影響は大きく受けています。特に印象に残っているのは、「社会保障は非常に重要な分野なのに、ちゃんと勉強している人がとても少ない」と嘆いていたことです。
韮原:確かに、先生はほかの医療・年金など社会保障関連の研究者たちの研究姿勢に苦言を呈していたように記憶しています。珍しくテレビ番組に出演されたときにも、民主党(当時)の岡田克也氏に制度の理解不足を指摘していました。高久教授も、そんな権丈先生のイズムを引き継いでいるのでしょうか?
高久:やっぱり、時代が変わっていくので、教育者としてのあり方も次の時代に合わせて再構築していかなければなりません。まったく同じやり方では、もう再現できないのです。
韮原:素人の私から見てという話にはなりますが、権丈先生には歴史や経済学説史、各国制度に対する深い知識を基にした政策提言をされている印象を持つ一方で、高久先生は「データの活用」を非常に重視していますよね。
高久:先生の政策に関する理解の深さは第一級です。その部分は今でも非常に参考になっています。その一方で、先生のあり方を今の社会に生かすために、私は「データ分析を学ばなければいけない」と早い段階から考えさせられましたね。つまり、先生からすべてを学ぶのではなく、「深く学んだこと」をほかの要素と組み合わせることで、今の時代にも再現可能になります。「変わらないためには変わり続けなくてはならない」というわけです。
韮原:社会のあり方や使える技術は変化していくものですからね。
高久:だからこそ、変化を前提に、自分が何を学べるのかを考える必要があります。良いやり方をしている先人がいて、その方法を単にまねるだけでは、20年後には再現不可能になってしまいます。それは私の教え子たちにも強く伝えています。
韮原:私も同意見で「すぐに学べる力」、つまり即習力が非常に重要だと思っています。その時代ごと、新たに生じた環境変化に適応した新しいスキルを身につける力こそが、もっとも大切だと。例えばビジネススクールで習うような経営戦略論のフレームワークは確かに今でもパワフルですが、AIなどの新技術が登場したり、国際情勢が混沌を極める中で、企業の競争環境が大きく変わっています。
高久:そうですね。
韮原:生成AIが出てきた、トランプ大統領が関税をかけてきた、中国が台湾に侵攻するかもしれない。そういった常に変化していく新技術の動向と国際情勢の中でいかに立ち振る舞えばよいのか。新たに必要になる知識やスキルをすぐに身に付けられる力そのものが今もっとも重要なスキルです。従来のように10年先を見越して「こういう人材を育てよう」と戦略を練るだけでは、とても間に合いません。
高久:むしろ「今、この瞬間に何が起きたのか」に即座に対応し、全知識と全人格をもって全力でぶつかる力こそが必要とされますね。
韮原:そうなんです。そして、その力を発揮するのは、今活躍しているリーダーではないかもしれません。「一騎当千」という言葉があるように、たったひとりの改革者が新たな時代を切り開いたり、ひとりの異端者が企業を逆境から救うといった千人分の活躍をするものです。ところで、我々がアカデミアとビジネスの異なる世界にあって、変化への対応力の重要性について話すのは偶然ではないように思います。大学時代に受けた教育の長期的な効果なのかもしれませんね。
高久:確かに。それが教育の長期的な効果ですね。研究というのは、「ひとつの真理を突き詰める」ことでもありますが、同時に、時代が変わったときに新しい問題にどう対応するかが求められます。だからこそ、「先生から学んだこと」だけをやっているだけでは、とても現代の課題には立ち向かえません。
韮原:ビジネスも同じで過去の成功モデルにこだわらず、今ここで為すべきことを見つけ実行する。それができるリーダーを育てていくことが重要なのだと思います。
掲載元:[人材育成イノベーター]韮原祐介の匠たちの育成哲学(サイゾー 2025年8月号掲載)
▶ 記事一覧はこちら
2025年06月30日